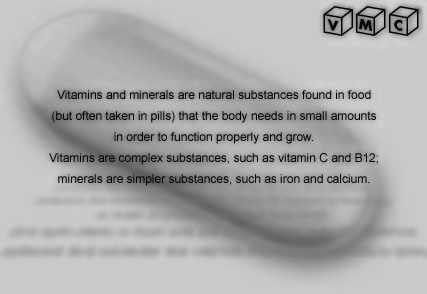~本当の意味~
「情けは人のためではなく、
いずれは巡って自分に返ってくるのであるから、
誰にでも親切にしておいた方が良い」
というのが原義である。
~誤解~
1960年代後半、若者を中心にこの言葉を
「情けは人のためではなく、
いずれは巡って自分に返ってくるのであるから、
誰にでも親切にしておいた方が良い」
というのが原義である。
~誤解~
1960年代後半、若者を中心にこの言葉を
「情けをかけることは、結局はその人のためにならない(のですべきではない)」
という意味だと思っている者が多いことが、マスコミなどで報じられた事が話題となった。
2000年ごろより、再びそのように解釈するものが増えていると報じられる。
2001年の文化庁による世論調査では、この語を前述のように誤用しているものは48.2%と、
正しく理解しているものの47.2%を上回ったという。
この誤解の根本は、「人の為ならず」の解釈を、
「人の為(に)成る+ず(打消)」(他人のために成ることはない)としてしまう所にあるとされる。
本来は「人の為なり(古語:「だ・である」という「断定」の意)+ず(打消)」、
すなわち「他人のためではない(→自分のためだ)」となるからである。
言葉の誤解が広まった背景には、
現代語が普及して古語の意味が国民の意識から次第に薄れつつあり、
その上に現代語での解釈と、現代的な価値観を合わせてしまった事があると言われる。
また「情けは質に置かれず」(経済的な意味のない情けは役に立たない)
とか、「情けが仇」(情けがかえって悪い結果になる)ということわざがあることも、
誤解を広めた一因でないかとも言われている。
そのため、時代の変化により
語の意味や解釈が変化してしまう例として、取り上げられることも多い。
(「助長」も孟子によれば、元は「急に成長させようとして無理に力を加えれば、かえって弊害が大きい」という意味であった)
なおいくつかの文章では、
「為ならず」の後ろにもう一文を加えて言葉の意味を分かりやすくしているものもある。
下記はその例である。
「情けは人の為ならず 身にまわる」(世話尽)
「情けは人の為ならず 巡り巡って己が(自分の)為」
フリー百科事典【ウィキペディア(Wikipedia)】抜粋。
という意味だと思っている者が多いことが、マスコミなどで報じられた事が話題となった。
2000年ごろより、再びそのように解釈するものが増えていると報じられる。
2001年の文化庁による世論調査では、この語を前述のように誤用しているものは48.2%と、
正しく理解しているものの47.2%を上回ったという。
この誤解の根本は、「人の為ならず」の解釈を、
「人の為(に)成る+ず(打消)」(他人のために成ることはない)としてしまう所にあるとされる。
本来は「人の為なり(古語:「だ・である」という「断定」の意)+ず(打消)」、
すなわち「他人のためではない(→自分のためだ)」となるからである。
言葉の誤解が広まった背景には、
現代語が普及して古語の意味が国民の意識から次第に薄れつつあり、
その上に現代語での解釈と、現代的な価値観を合わせてしまった事があると言われる。
また「情けは質に置かれず」(経済的な意味のない情けは役に立たない)
とか、「情けが仇」(情けがかえって悪い結果になる)ということわざがあることも、
誤解を広めた一因でないかとも言われている。
そのため、時代の変化により
語の意味や解釈が変化してしまう例として、取り上げられることも多い。
(「助長」も孟子によれば、元は「急に成長させようとして無理に力を加えれば、かえって弊害が大きい」という意味であった)
なおいくつかの文章では、
「為ならず」の後ろにもう一文を加えて言葉の意味を分かりやすくしているものもある。
下記はその例である。
「情けは人の為ならず 身にまわる」(世話尽)
「情けは人の為ならず 巡り巡って己が(自分の)為」
フリー百科事典【ウィキペディア(Wikipedia)】抜粋。
PR
~人類の夢は、果敢無き現実~
初夢(はつゆめ)とは、新年に初めて見る夢。
この夢の内容で、1年の吉凶を占う風習がある。
1月1日から1月2日、または1月2日から1月3日にかけての夜に見る夢を初夢とする。
室町時代ごろから、良い夢を見るには、七福神の乗った宝船の絵に
「永き世の 遠(とお)の眠(ねぶ)りの 皆目覚め 波乗り船の 音の良きかな」
という回文の歌を書いたものを枕の下に入れて眠ると良いとされている。
これでも悪い夢を見た時は、翌朝、宝船の絵を川に流して縁起直しをする。
初夢に見ると縁起が良いものを表すことわざに
「一富士(いちふじ)、二鷹(にたか)、三茄子(さんなすび)」というものがある。
この三つの組み合わせは、江戸時代初期にはすでにあったが、その起源については諸説ある。
また、「四扇(しおうぎ)、五多波姑(ごたばこ)、六座頭(ろくざとう)」と続くこともある。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』抜粋。
初夢(はつゆめ)とは、新年に初めて見る夢。
この夢の内容で、1年の吉凶を占う風習がある。
1月1日から1月2日、または1月2日から1月3日にかけての夜に見る夢を初夢とする。
室町時代ごろから、良い夢を見るには、七福神の乗った宝船の絵に
「永き世の 遠(とお)の眠(ねぶ)りの 皆目覚め 波乗り船の 音の良きかな」
という回文の歌を書いたものを枕の下に入れて眠ると良いとされている。
これでも悪い夢を見た時は、翌朝、宝船の絵を川に流して縁起直しをする。
初夢に見ると縁起が良いものを表すことわざに
「一富士(いちふじ)、二鷹(にたか)、三茄子(さんなすび)」というものがある。
この三つの組み合わせは、江戸時代初期にはすでにあったが、その起源については諸説ある。
また、「四扇(しおうぎ)、五多波姑(ごたばこ)、六座頭(ろくざとう)」と続くこともある。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』抜粋。